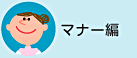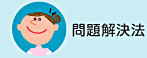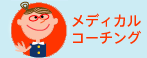| |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
| |
第2回 院内の情報共有円滑化講座(2)
(部下や他職種との上手いコミュニケーションの仕方)
|
まず、第一の側面は、患者との関係です。
患者さんと医療従事者との関係は、大きく変化しています。従来の医師や看護師が患者を管理して治療や看護するという、上下の関係ではなく、お互いが対等の立場で医療行為や看護行為を提供する側とされる側にとの関係に変化してきました。
従来は、医師や看護師が患者と比較して疾病に対して絶対の知識と経験を持っておりそれらの知識や経験に沿って、医療従事者が一方的に患者に対して治療を施し、その治療を患者が受けるという関係でした。ところが最近はその関係が変化してきました。
医療従事者は、患者の疾病に対する情報提供者であり、患者はその情報を元に、自分の治療法方について決定をしていき、その決定に基づいて、医療従事者は患者の治療をするという関係に変化して来ました。
しかし、その関係構築が有効に働いているといえるでしょうか?
まず、患者サイドの問題は、患者にはあらゆるレベルの人がいます。インターネットや書籍で自分の疾病について研究している人から、すべて医師にお任せという意識の人まで、それこそ100人の患者に100のレベルがあると言っても言い過ぎではないかもしれません。
つまり、今医療従事者に求められるスキルは、高いレベルの治療技術や看護技術以外に、患者に情報を提供してその情報を理解してもらう、説明能力が求められるのです。そして、患者のレベルを把握し、望んでいる治療をおこなわなければなりません。
第二の側面は、医療従事者間との関係です。
従来は、医師が中心で医師の指示により、各職種のスタッフは動いていました。診療科も今ほど細分化されていなかったために、スタッフは医師中心に動いておれば、あまり問題は発生しなかった時代が長く続きました。
ところが、診療科が細分化され、同時に先端機器の導入は各スタッフでの専門技術が高度化し、それぞれがある程度独立して存在する組織に変化してきました。つまり、専門化集団の縦割り組織が完成したのです。
主治医は、確かに患者の容態に対しての責任者ですが、看護師、コメディカル等もまた、独立した組織として患者に対応します。それらの職種間での患者の情報の共有が最も大切なものに変化しているのです。
診療が細分化、専門化され、組織が巨大化すればするほど、患者の情報は共有しがたくなります。
電子カルテも情報共有の一手段ではありますが、組織間情報伝達の方法や、治療の責任者としての主治医と、患者の情報管理者としての責任者を分離する必要があるかも知れません。
つまり、仕組みとして、職種間コミュニケーションができるようにしなければなりません。
第三の側面は、医療従事者の価値観の多様化です。
これは医療従事者だけの問題ではありません。あらゆる企業や団体で発生していることです。
従来は、同じような教育レベルと、考え方をもった人は企業に就職をして働いていました。その結果、よく言われる“あ・うん”の呼吸がスタッフ間で存在していました。しかし、現在は、企業内でも、今まで考えられなかった人たちが働いています。
正社員、契約社員、派遣社員、外国人労働者といったあらゆる経歴とレベルの人がはたらいているために、“あ・うん”の呼吸が通用しなくなっています。
医療機関は一般の企業と違って、入職する前には必ず各専門の分野の学校を卒業しています。ですからある程度共通の価値観を持っているはずです。
しかし、医療機関においても同様な問題が起こっています。特に組織が大きくなればなるほどその傾向は大きいです。
ただでさえ、専門家集団であるが故に組織間伝達が困難な上に、若いスタッフとの価値観のずれによるコミュニケーションの隔絶が発生しています。その結果、同一病院としての整合性が取れていない事態が発生します。
確かに従来の病院と患者の関係は、前述したように、一方的に疾病を治すという関係でしたが、現在は、情報を提供し、その提供方法も患者が理解しやすいようにしなければなりません。医師や看護師の仕事は大きく変化しています。
つまり、疾病を治療すると言うだけでは、その義務の半分しか果たしていないのです。ビジネスパーソンとしての側面も必要になるのです。
同時に病院も、職員としての医師や看護師に整合性をもたさなければなりません。あの医師とこの医師の対応が違う、と言うことは、病院としての信頼性を疑われることになります。
次回は、具体的な例を挙げてみます。
|
| |
|
|
 |
| |
|
 |
|
| |
|
 |
| |
|