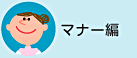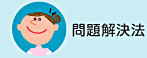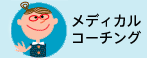| |
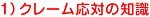 |
| |
| 患者さんからの苦情やクレームを受けることは、誰にとっても厭なことです。誰でも苦情を言われたいとは思いません。まして、医療機関で働く看護士さん達は、患者さんのために、一生懸命仕事をしているわけですから、患者さんからの苦情やクレームは、「寝耳に水」と感じたり「ちょっと勘違いじゃないの」と思うこともあります。 |
| |
| 実際、アメリカの調査機関「e-サスティファイ」の調査では、持ち込まれる苦情の40%は、顧客の過度な期待や、思い違いが原因であることが発表されています。しかし、理由が何であれ、患者さんの声は、医療機関が気がつかないことを教えてくれる「天の声」の性格もあります。 |
| |
| 患者さんは以下5点のようなときに、不安を感じます。 |
| |
1)
2)
3)
4)
5) |
信頼を裏切られた時(医療技術や看護技術等の専門分野)
期待した治療や、説明が受けられていないと感じたとき(インフォームドコンセントや応対)
建物の掃除が行き届いてなく、また職員の身だしなみが不潔だったり、
だらしなく医療機関の職員らしくないと感じた時(ハード面や身だしなみ)
自分が大切に扱われていないと感じた時(共感ある対応力)
しっかりした対応が受けられていないと感じた時(説明力や応対力) |
| |
どのような理由で患者さんが苦情を言ってくるかは、話を聞くまではわかりません。
そのために苦情を聞く心構えを以下にあげます。 |
| |
●顧客が不満を持っているということが唯一の事実
●自分たちが原因で不満を生じさせたことに対する理解と共感
●先入観は持たない
●まず患者さんの言うことをきちんと聞くということを理解していただく。 |
| |
| 上の気持ちを患者さんに知っていただくためのフローは以下の通りです。 |
| |
1)
2)
3)
4)
5)
6) |
来られた患者さんに気分を害されたことについてお詫びをする。
相手の言うことをきちんと聞く。(最低5分は聞きましょう)
確認のためい要約したり、質問をします。
1.問題が解決出来る場合は、解決案を具体的に提示し、患者さんの理解を得ます。
2.出来ない場合は、その旨と理由をはっきりと言います。
但し、ご希望に添えない事に対するお詫びと共感を忘れずに。
3.即答出来ない場合も、その旨を説明し、いつごろまでに回答が出来るかを伝える。
話が終わったら、わざわざ苦情を言いにきたお礼を言う。
報告書に記入し、検討会で当該事情を検討する。 |
| |
患者対応塾(R)では、次回より、実際の実例に即したクレーム応対についてご案内いたします。
ご期待ください |
| |